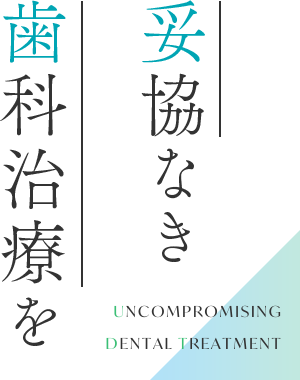
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
休診日:日曜、祝日
※午前受付が12:30まで、午後受付が18:00までとなります
厚生労働省指定単独型臨床研修施設

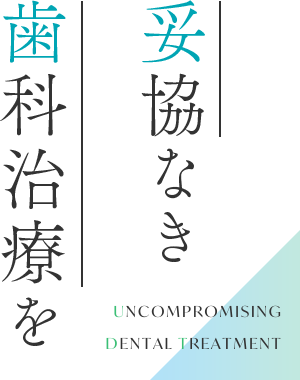
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
休診日:日曜、祝日
※午前受付が12:30まで、午後受付が18:00までとなります
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
休診日:日曜、祝日
※午前受付が12:30まで、午後受付が18:00までとなります
2023年12月27日(水)午後診療~2024年1月3日(水)まで年末年始の休診となります
1月4日(木)より通常診療いたします🎍
12/26(火)、2Fチャーリー王国(小児歯科)にてイベントを行います🎅✨
※完全予約制になります 詳しくはこちら
10/30(月).31(火)、2Fチャーリー王国(小児歯科)にてイベントを行います🎃✨
詳しくはこちら

最初のスプーン一杯から
最期のスプーン一杯まで
健康的に過ごしていただけるように
当院はお口のキュア、ケアを通じて地域の皆様の全身の健康にコミットする歯科医院を目指します。そのために患者様お一人毎に掛かりつけ歯科衛生士が対応し、歯科医師、歯科衛生士と患者様の3身1体でお口の健康を維持してまいります。また、妥協なき、歯科治療のため新鋭の設備、施設をご用意し、技術の研鑽を日々行っています。「何でもご相談ください」すべてはそこから始まります。





各分野の専門医と歯科衛生士が
皆様の歯の健康をサポート
松代歯科医院は、地域の中でも規模の大きい歯科医院であり、歯科医師、歯科衛生士が多数在籍しています。各治療の専門医が治療を担当し、定期的な歯のメンテナンスなどは歯科衛生士が一人ひとりに合った丁寧な治療を提供いたします。



新鋭設備による確かな診断と
質の高い治療を提供
精度が高く、幅広い治療を提供するために歯科用CT、マイクロスコープ、iTeroなど充実した設備を多数導入しています。設備を充実させることで的確な診断、治療を行うことが可能となります。







どのような方にも
治療を受けていただける
歯科医院
どの世代の方にも治療を受けていただけるよう、キッズ専用フロアや個室診療室などの院内環境を整えています。車いすやベビーカーでご来院いただきやすいようにバリアフリー設計となっており、通院が困難な方には訪問診療に対応しています。幅広く治療方法をご用意していますので、お口のお困りごとはお気軽にご相談ください。


楽しいキッズ専用フロア
をご用意
当院は、お子様が楽しく歯科医院に通っていただけるようにワクワクがつまったキッズ専用の診療フロアがございます。ただ治療を受けに来るところではなく、気軽に遊に行けるような歯医者さんを目指しています。
当院はお子様の成長とお口の健康を見守るプログラムをご用意しています。
お子様の呼吸の仕方や、食べ方などに不安を感じた場合はご相談ください。

徹底した衛生管理で
より安心できる診療を提供します
当院では、厳しいヨーロッパ基準を満たした滅菌器を導入し、患者様ごとに治療器具を滅菌しています。
ご来院いただくすべての患者様に安心して治療を受けていただくために、衛生管理を徹底しています。



いつまでもご自身の歯で過ごすために、むし歯や歯周病は早めの治療が大切です。
治療

検査や健診、歯のメンテナンスを受けることで、歯が悪くなることを防ぎます。日々の予防は健康への近道です。
予防

美しく、健康的な口元は周りからの印象も変え輝く日常へ
導きます。
審美
